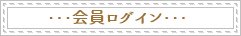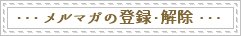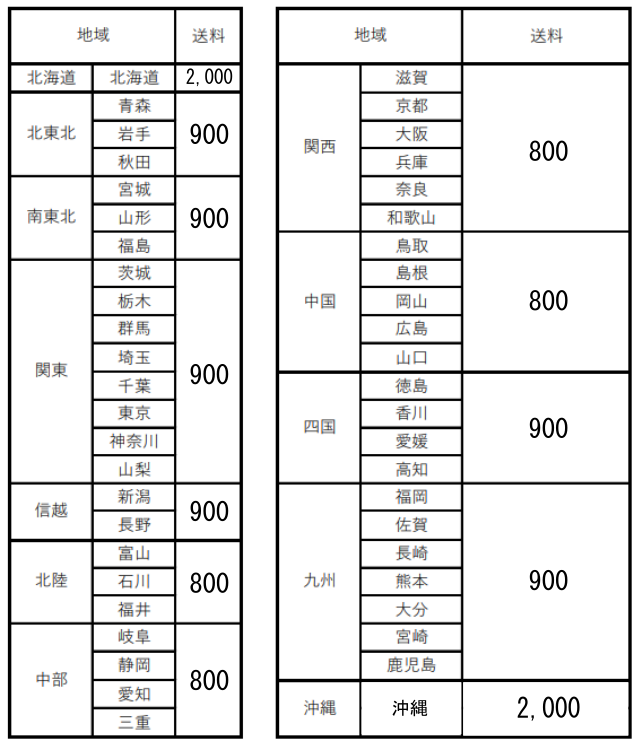![]()
![]()
![]()
![]()
 セットでお得!【セット割】
セットでお得!【セット割】
 健康茶
健康茶
【ブレンド健康茶】
明日葉
あずき茶
いちょう
うこん
うらじろがし溶石茶
柿の葉
カバノアナ茸(白樺茸)
ギムネマシルベスタ茶
ギャバロン
クマ笹
クミスクチン
くろまめ茶
くわの葉
黒文字
ゴーヤ
ごぼう
サラシア
シジュウム・グァバ
紫蘇
ジャスミン
生姜
スギナ
杉の葉
そば・韃靼そば
タヒボの精
たんぽぽ
甜茶
とうもろこし茶
どくだみ
杜仲葉
なた豆
はと麦
バナ葉茶
はぶ茶
びわ
マテ
メグスリノキ
よもぎ
羅布麻
ルイボスティー
 日本茶
日本茶
 麦茶
麦茶
 和紅茶
和紅茶
 烏龍茶/プアール茶
烏龍茶/プアール茶
 粉末飲料/インスタント/他
粉末飲料/インスタント/他
 エコパック
エコパック
 コーヒー
コーヒー
 健康食品/食品
健康食品/食品
 お菓子
お菓子
 うどん/麺類
うどん/麺類
 お茶パック
お茶パック
 ご進物
ご進物
◎お煎茶コラム
煎茶以外の日本茶いろいろ(3)
今回こちらでご紹介するのは、「番茶」・「ほうじ茶」・「玄米茶」です。
いずれも、日常のお茶として日本茶の中でも身近な存在。
熱々のお湯をたっぷり注いでふうふう言いながら飲むのが美味しい、手軽でいて香りも充分に楽しめるお茶です。
私たちにほっこりと安心感を与えてくれるお茶の魅力に迫ります。
1.番茶
◎みなさんの地域で飲まれる「番茶」は何色のお茶ですか??
番茶といえば日常のお茶。
これはどの地域でも共通してもつ「番茶」に対するイメージではないでしょうか。
番茶の定義は一応あるのですが、実のところ地域によって「番茶」の意味するところがちょっと違います。
まずその色。
関東や東北南部、静岡県などの中部地方の大部分、鹿児島県などの九州地区では、番茶と言えば緑色。
一方、北海道、東北北部、北陸、関西、中国・四国地方では、番茶と言えば茶色いお茶です。
茶色い番茶は、製造工程の最後で茶葉を炒っているので茶色くなります。
この製法で作られたお茶を「ほうじ茶」と区別して「ほうじ番茶」とも呼び、この「ほうじ番茶」が日常のお茶として飲まれる 地方では、番茶とは「ほうじ番茶」のことを指します。
ですので、ほうじ番茶が日常茶となっている地域では、番茶とは茶色いお茶なのです。
◎番茶とは
番茶は一口に定義付けするのが難しいお茶です。
番茶は日常茶というだけあって、地方独特の製法や飲み方があり、その地域の生活習慣や食文化に溶け込んだお茶と言えます。
日本茶業中央会の定義によると、
番茶とは「大きい型の煎茶。原料が古葉や硬い新葉で、おおむね扁平な形をしている。
原料が硬化してから摘採して製造するものと、荒茶の仕上げ中に選別されるものと二通りある」
となっています。
大雑把に言うと、下級煎茶という位置付けです。
成長した茶葉が原料である番茶は、煎茶に比べてタンニンの含有量が多く、逆に旨味成分のアミノ酸や苦味成分のカフェインは 少なくなります。
そのため、すっきりとグクゴク飲める味わいが特徴です。
地方によって独自の番茶が数多くあり、京番茶や阿波番茶などが有名。
主に関西で作られる、煎茶の仕上げ加工の工程で選別された大型の葉が原料となる番茶は、「川柳」「青柳」と呼ばれ関東の番 茶とは区別されます。
《香り》

《甘み・旨み》

《渋味》

《コク》

2.ほうじ茶
ほうじ茶は煎茶や番茶、茎茶などを褐色になるまで高温で焙煎したお茶のことを指します。
一般的には一番茶の遅い時期の葉を原料としたものが上質であるとされます。
いわゆる上級茶の類ではありませんが、香ばしい香りと口の中をさっぱりとさせてくれる飲み口は、日常のお茶として不動の人気を誇ります。
ほうじ茶は大正末期、お茶が売れない時期が続いて在庫を抱えた京都の茶商が、苦肉の策で生み出したものだと言われています。
茶葉を高温で焙じることで「焙焼香(ばいしょうか)」と呼ばれる独特の香ばしい香りが付き、特に茎茶を焙じた「茎ほうじ茶」はこの焙焼香がよりいっそう楽しめます。
熱々のお湯で淹れると香りがよく立ちます。
ほうじ茶はセラミック粒や電気、ガスなどを用いて約200℃の高温で焙じられ、すぐに冷却して作られます。
自宅でも古くなった煎茶や番茶をフライパンで炒れば、意外と簡単に作ることができます。
ほうじ茶はカフェイン含有量が少なく、昔から妊娠中や授乳中の時にも飲まれていました。
これは焙じることで茶に含まれるカフェインが昇華され、含有量が少なくなるからです。
また、ほうじ茶はお家でも簡単に作れます。
詳しくは◎お煎茶コラム:「お家の煎茶でほうじ茶作り」をご覧ください。
《香り》

《甘み・旨み》

《渋味》

《コク》

3.玄米茶
玄米茶もほうじ茶と並んで香ばしさが人気のお茶です。
「玄米茶」と呼ばれてはいますが、一般的に使われているのは玄米ではなく白米です。
これは玄米よりも白米の方が香りが良いためで、一度蒸した白米を乾燥させてから褐色になるまで炒ったものを使います。
これに煎茶や川柳、青柳または番茶などをほぼ同量の割合で混ぜたものが玄米茶です。
戦前、鏡開きの時にできる餅の破片を勿体無いと考えた京都の茶商が、これを炒って煎茶に混ぜたのが始まりだと言われていま す。
香ばしい香りとあっさりとした味は老若男女問わず人気があり、値段も煎茶よりもお手頃なので気軽に飲め、お茶漬けとも相性 が良いです。
炒った米がブレンドされていることで、煎茶や番茶の使用量が少なくなることから、煎茶より一杯あたりのカフェイン量が少ないので、そういった意味でもお子様やお年寄りの方にもお勧めできるお茶です。
玄米茶の香ばしさは、米を焙煎することで引き出され、その品質は煎茶よりもむしろ米の質に左右されます。
香ばしさは爆ぜた米よりも、狐色の炒った米のほうから出るので爆ぜた米の割合が多いものは下級品となります。
◎玄米茶の美味しい淹れ方
玄米茶を美味しく淹れるには熱湯を使用し短時間で抽出するのがコツです。
茶葉を急須に茶葉を約15g入れ、熱湯を注ぐと香ばしい香りが立ち上がります。
お湯を注いだら40秒ほど煎茶の葉が開くのを待ちます。
時間をかけすぎますと煎茶の渋み成分タンニンが多く出て渋みが増してしまいます。
湯呑みに注ぐ時は最後の一滴まで注ぎきりましょう。
二煎目をいただく場合は、急須に湯を入れたらすぐ湯のみに注いでください。
玄米茶は二煎目で旨みがほとんど出尽くしますので次からは茶葉を取り替えましょう。
普段煎茶を飲む方でも、ブレンド用の 「玄米茶の素」が販売されていますので、ご自宅の煎茶にブレンドしていつもとは違った味を楽しんでみるのも良いですね。
《香り》

《甘み・旨み》

《渋味》

《コク》

◎ 山本園t−net 売れ筋ランキング↓↓↓
-
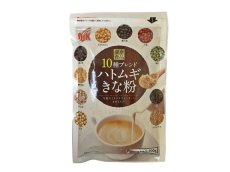
 【クリポス】10種ブレンドハトムギきな粉 200g
【クリポス】10種ブレンドハトムギきな粉 200g
652円(税48円)
-

丸はと麦茶ゴールド 粒350g(1袋/1ケース)
680円(税50円)
-

野草健康茶【ノンカフェイン16種調合】リーフ500g(1袋/1ケース)
712円(税52円)

 【SALE】セール
【SALE】セール ケース割引対象商品
ケース割引対象商品 ノンカフェインのお茶
ノンカフェインのお茶 開花の季節に
開花の季節に 血糖値が気になる方へ
血糖値が気になる方へ スタイルが気になる方へ
スタイルが気になる方へ オーガニック(有機)
オーガニック(有機) 機能性表示食品/特保
機能性表示食品/特保 業務用
業務用 【クリポス】対応
【クリポス】対応