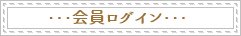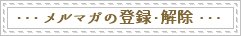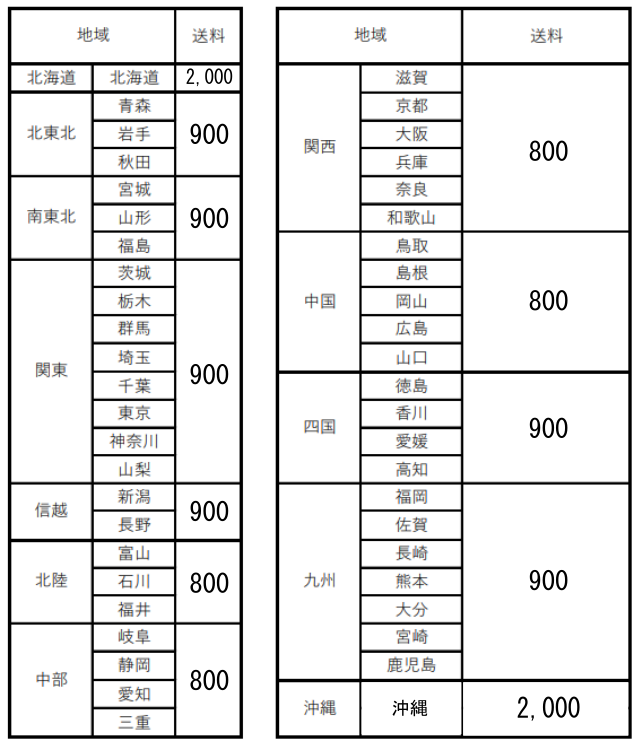![]()
![]()
![]()
![]()
 セットでお得!【セット割】
セットでお得!【セット割】
 健康茶
健康茶
【ブレンド健康茶】
明日葉
あずき茶
いちょう
うこん
うらじろがし溶石茶
柿の葉
カバノアナ茸(白樺茸)
ギムネマシルベスタ茶
ギャバロン
クマ笹
クミスクチン
くろまめ茶
くわの葉
黒文字
ゴーヤ
ごぼう
サラシア
シジュウム・グァバ
紫蘇
ジャスミン
生姜
スギナ
杉の葉
そば・韃靼そば
タヒボの精
たんぽぽ
甜茶
とうもろこし茶
どくだみ
杜仲葉
なた豆
はと麦
バナ葉茶
はぶ茶
びわ
マテ
メグスリノキ
よもぎ
羅布麻
ルイボスティー
 日本茶
日本茶
 麦茶
麦茶
 和紅茶
和紅茶
 烏龍茶/プアール茶
烏龍茶/プアール茶
 粉末飲料/インスタント/他
粉末飲料/インスタント/他
 エコパック
エコパック
 コーヒー
コーヒー
 健康食品/食品
健康食品/食品
 お菓子
お菓子
 うどん/麺類
うどん/麺類
 お茶パック
お茶パック
 ご進物
ご進物
◎お煎茶コラム
煎茶以外の日本茶いろいろ(1)
日本茶とは、日本でよく飲まれるお茶の総称です。
そのうち、約70%を占めると言われる煎茶は日本茶の代表です。
しかし、煎茶以外にも玉露や抹茶、番茶や茎茶など美味しい日本茶がたくさんあります。
ここでは玉露・かぶせ茶・抹茶についてご紹介したいと思います。
1.玉露
玉露は日本茶の最高峰とも称される高級茶です。
玉露も煎茶と同じ茶の樹から作られ、製茶方法も同じなのですが、茶樹の栽培方法が異なります。
煎茶用の茶園では、日光を浴びたまま茶樹が育てられる「露天栽培」が行われるのに対し、玉露用の茶園では新芽が出てか ら摘み取りまでの3週間ほど覆いを被せ、日光を遮断して栽培する「被覆栽培」が行われます。
新芽が1〜2枚開き始めると遮光率70〜80%の覆いを被せ、その1週間〜10日後、今度はさらに遮光率の高い覆いをし遮光率 95〜98%にします。
こうして栽培された茶葉は、覆いを被せ始めてから約20日後に摘採されます。
茶葉に含まれるアミノ酸の一種でテアニンという旨み成分は、日光を浴びると光合成により苦味や渋味をもつカテ キンという成分に変化します。
よって、遮光して栽培することにより、旨み成分テアニンの減少を抑えることができるのです。
さらに、さっぱりとした苦味を醸し出すカフェインや、緑色の色素をもつ葉緑素クロロフィルも被覆栽培の方が露天栽培よ りも増加します。
被覆栽培で育てられた茶葉を原料とする玉露は、煎茶と比べて濃厚な旨みの中にもさっぱりとした苦渋味が感じられ、濃緑 色が目にも美しい、上品な味わいのお茶に仕上がるのです。
また、被覆栽培を行うと青海苔を思わせるような「覆い香」が付き、独特の香りも楽しめます。
《香り》

《甘み・旨み》

《渋味》

《コク》

◎玉露の美味しい淹れ方(2人分)
玉露は濃厚な旨みを少量ずつ楽しむお茶ですから急須も茶碗も非常に小さいものを使います。
急須が90cc、茶碗が40ccくらいが大きさの目安です。
玉露は濃厚な旨み、甘み、軽い苦味と渋味のバランスを楽しむお茶です。
玉露の特徴を存分に引き出せるように淹れてみましょう。
ポイントは湯の温度です。
旨み成分のテアニンは低温でも抽出されますが、一方で渋み成分であるカテキンやカフェインは高温の方が抽出されやすい 成分です。
玉露では湯の温度を50〜60℃と低温にし、浸出時間を2分〜2分半と長めに淹れることで、旨み・甘み・苦味・渋味の バランスが味わえるようになります。
1.お湯を用意する
沸騰させた湯を、湯冷まし→急須→茶碗の順に移していきます。
お湯の量は約90cc。
※季節や材質によっても異なりますが、お湯は一度他の器に移すと約10℃温度が下がります。
50〜60℃のお湯を用意するには、湯冷ましがあると便利です。
2.茶葉を急須に入れる
2人分で約8g(ティースプーン大さじ山盛り1杯)の茶葉を先ほど温めた急須に入れます。
3.湯を注ぐ
茶碗の湯を急須に注ぎ、約2分半待ちます。
この時急須をゆすったりすると雑味が出ますので、じっと静かに待ちましょう。
4.茶碗に廻し注ぐ
お茶を分量や水色の濃淡が均一になるように「廻し注ぎ」で淹れます。
※最後の一滴は旨みが凝縮されたエキスです。
最後の一滴まで注ぎ切るようにしましょう。
5.二煎目
二煎目は70℃〜80℃のお湯を注ぎ、待たずにさっと淹れます。
2.かぶせ茶
かぶせ茶は「冠茶」とも書き、玉露と同じく被覆栽培で栽培された茶の葉から作られます。
玉露と異なるのは、遮光されている期間や遮光率です。
かぶせ茶の場合は玉露より被覆する期間が短く、茶摘み前の約1週間覆いを被せます。
また、遮光率も玉露の時より低く、約50%の覆いを被せて栽培されます。
かぶせ茶は玉露と煎茶のちょうど中間といった茶種で、青海苔のような覆い香が感じられ、苦すぎず甘すぎず穏やかな風味を持 ちます。
お茶は淹れる時の湯の温度で味が変化しますが、かぶせ茶は玉露と煎茶の中間と言うだけあって、低温のお湯で淹れると玉露を 思わせる旨みと甘みを感じられる味に、熱湯で淹れると煎茶のようなさっぱりした味になる変幻自在の繊細なお茶でもあります 。
《香り》

《甘み・旨み》

《渋味》

《コク》

◎かぶせ茶の美味しい淹れ方(2人分)
●甘みを引き出してまろやかに
1.お湯を用意する
沸騰させた湯を、湯冷まし→急須→茶碗の順に移して60℃位のお湯を用意します。
お湯の量は約150cc。
※季節や材質によっても異なりますが、お湯は一度他の器に移すと約10℃温度が下がります。
50〜60℃のお湯を用意するには、湯冷ましがあると便利です。
2.茶葉を急須に入れる
2人分で約8g(ティースプーン大さじ山盛り1杯)の茶葉を先ほど温めた急須に入れます。
3.湯を注ぐ
茶碗の湯を急須に注ぎ、約1分半待ちます。
この時急須をゆすったりすると雑味が出ますので、じっと静かに待ちましょう。
4.茶碗に廻し注ぐ
お茶を分量や水色の濃淡が均一になるように「廻し注ぎ」で淹れます。
※最後の一滴は旨みが凝縮されたエキスです。
最後の一滴まで注ぎ切るようにしましょう。
5.二煎目
二煎目は熱湯を直接注ぎ、待たずにさっと淹れます。
●苦渋味を引出してさっぱりと
1.お湯を用意する
お湯の温度は80℃位、量は150cc位が目安です。
※沸騰させたお湯を一度茶碗に入れてから、茶葉を入れた急須に注ぐと80℃位で淹れられます。
2.茶葉を急須に入れる
2人分で約8g(ティースプーン大さじ山盛り1杯)の茶葉を急須に入れます。
3.湯を注ぐ
茶碗の湯を急須に注ぎ、約40秒待ちます。
この時急須をゆすったりすると雑味が出ますので、じっと静かに待ちましょう。
4.茶碗に廻し注ぐ
お茶を分量や水色の濃淡が均一になるように「廻し注ぎ」で淹れます。
※最後の一滴は旨みが凝縮されたエキスです。
最後の一滴まで注ぎ切るようにしましょう。
5.二煎目
二煎目は熱湯を直接注ぎ、待たずにさっと淹れます。
3.抹茶
緑茶を石臼で挽いて細かい微粉末にしたものを抹茶と言います。
抹茶は茶道などで使われる、ちょっと格式の高いお茶というイメージがある反面、スイーツやアイスなど普段よく口にするもの にも使われ、最近では外国人の方にも人気が高いお茶ですね。
先ほど、抹茶は微粉末と言いましたが、どれくらい細かいのでしょう。
抹茶の粒子は1〜20ミクロン(1ミクロン=1ミリメートルの1000分の1)で、小麦粉や片栗粉の約半分の粒子の大きさなんです。
その中でも石臼で挽いた1〜5ミクロンの抹茶はとりわけ良質なものであるとされています。
もしかすると、テレビなどで石臼を使って抹茶を作るシーンを見たことがある方もいらっしゃるかもしれませんね。
ただ、普通の緑茶を石臼で挽いて抹茶にするのかと言うと、そうではありません。
抹茶を作るには原料に「碾茶(てんちゃ)」と呼ばれるお茶を使います。
「碾茶」は、玉露と同じように日光を遮る被覆栽培で栽培された茶葉を、揉まずに乾燥させ、茎や葉脈を取り除いたお茶のこと です。
被覆栽培によって渋味が抑えられた柔らかい新芽は、品質と茶樹を守るため5月上旬から中旬にかけて年に一度だけ摘まれます 。
ちなみに、ちょっと荒っぽい言い方ですが、揉まずに乾燥させると碾茶になりますが、揉んで製茶すると玉露になります。
このことから、抹茶の原料となる碾茶は上質なものであることがご想像いただけるかと思います。
セラミック製の臼や石臼で挽いて抹茶は作られますが、抹茶は粉末であるがゆえ湿気に弱く長期保存には向いていないため、出 荷の前に挽き、それまでは碾茶を温除湿のよいところで保存する方法が一般的です。
こうすることで、湿気を嫌う抹茶を良い状態で出荷することができるだけでなく、碾茶そのものも適度に熟成されて味に深みが 増すのです。
《香り》

《甘み・旨み》

《渋味》

《コク》

◎自宅でできる!抹茶の簡単な点て方(1人分)
抹茶は茶道で飲むお茶でしょ?私は茶道のさの字も知らないから…、道具もないし…、なんとなく敷居が高いわ…などと思って いませんか?
そんなことは全然ありません!
抹茶用の茶碗が無くてもお家にあるカフェオレボウルや口広の茶碗があればOKです。
あと1つ、「茶筅(ちゃせん)」を用意すれば簡単にお家でも点てて飲んでいただけます!
茶筅がお家に無いという方も、ネットなどで1,000円以下の物もたくさん販売されていますのでこの機会に購入されても良いと 思います。
また、100円ショップなどで販売されている小さい泡だて器などでも代用可能ですので、一度それで試してみるのも良いかも しれません。
抹茶は緑茶をまるごと粉末にしたもの。
実は抹茶は緑茶に含まれる健康に良い成分をまるごと全部いただける隠れた健康茶なんです!
敷居が高いと二の足を踏んでいる場合ではありません!
お家でも抹茶を点てて飲んでみましょう。
1.お湯を用意する
お湯の温度は70℃〜80℃位、量は100cc/人が目安です。
※沸かしたお湯を湯冷ましに入れ、少しおいてから使うと良いでしょう。
※お湯の温度が低すぎると泡立ちが悪くなります。
2.抹茶を茶漉しでふるう
抹茶の量はティースプーン1匙(約2g)/人が目安です。
ダマになりやすいのでひと手間かけて茶漉しでふるってあげると美味しくいただけます。
面倒な時や茶漉しが無い場合は、乾いた茶碗に直接抹茶を入れて茶筅でダマを潰しても良いです。
3.茶碗に湯を注ぎ点てる
抹茶を入れた茶碗に先ほど湯冷ましに入れておいたお湯を静かに注ぎ、まんべんなく茶筅でかき混ぜていきます。
コツは「m」の字を書くように混ぜること。
最初は大きい泡ですが、だんだん細かくなってきます。
最後に表面付近を茶筅で撫でるように混ぜてあげると、さらにきめ細かい泡が立ちます。
混ぜ終わったら、「の」の字を書くようにして最後にそっと引き上げます。
◎ 山本園t−net 売れ筋ランキング↓↓↓
-
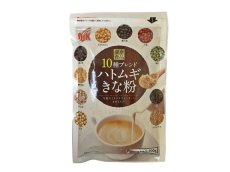
 【クリポス】10種ブレンドハトムギきな粉 200g
【クリポス】10種ブレンドハトムギきな粉 200g
652円(税48円)
-

丸はと麦茶ゴールド 粒350g(1袋/1ケース)
680円(税50円)
-

野草健康茶【ノンカフェイン16種調合】リーフ500g(1袋/1ケース)
712円(税52円)

 【SALE】セール
【SALE】セール ケース割引対象商品
ケース割引対象商品 ノンカフェインのお茶
ノンカフェインのお茶 開花の季節に
開花の季節に 血糖値が気になる方へ
血糖値が気になる方へ スタイルが気になる方へ
スタイルが気になる方へ オーガニック(有機)
オーガニック(有機) 機能性表示食品/特保
機能性表示食品/特保 業務用
業務用 【クリポス】対応
【クリポス】対応